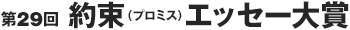2009年
第14回入賞作品
優秀賞
「祖母との約束」 飯田 みゆき(79歳 農業)
遠州地方特有の冷たい空っ風の中で畑仕事に精出す私の背を、色褪せて布目から真綿の吹き出たちゃんちゃんこが、冬の日を溜め込んでふんわりと包む。
このちゃんちゃんこはもとは美しい晴着で、初孫の私をこよなく愛した祖母が、心を込めて整えてくれた貴重な品であった。
昭和五年、稲作と養蚕を家業とする農家に生まれた私は、蚕が桑を食(は)む小雨の様な音の中で祖母に抱かれて眠り育ったが、戦中戦後の深刻な食糧難は桑畑を次々と麦や甘藷畑に変え、やがて養蚕は衰退してしまった。
そんな中で娘時代を迎えた私に、この物不足の中で新しい晴着の入手など到底無理と考えた祖母は、一念発起し自らの手でそれを用意しようと思い立つ。
養蚕の経験を持つ祖母は、早速納屋の二階に蚕棚を組み、畑の境界に点々と残されていた桑を摘み蚕を飼い始めた。そして多忙な農作業の合間(あいま)や夜業(よな)べ仕事の傍ら寸暇を惜しんで、春蚕(はるこ)の掃き立てから晩蚕の上簇(じょうぞく)まで、祖母の小さな養蚕は繰返し続けられた。一日に何度も桑籠を抱えて納屋を出入りする祖母の姿は、足取りも軽く楽しげに見えた。
そして農閑期の冬、祖母は溜めて置いた繭を夜毎ひたすら糸に紡ぐ。湯気の立つ鍋の中の繭達は祖母の絶妙な手さばきで、縒をかけられ次々と糸車に巻き取られていく。糸車の軽い響きと祖母の昔語りに更ける冬の夜は、寒く貧しかったが私には至福の時間であった。
こうして紡ぎ終えた生糸の束は、知り合いの機屋で光沢のある見事な絹布となり、すぐ染めに出され、母の手で鴇色地(ときいろじ)に花模様の美しい晴着に仕立てられたのである。
二十歳(はたち)の正月、私は祖母が二年がかりの丹精の晴着に初めて手を通した。
「ええ娘(こ)になった。ええ娘(こ)になったのう。」
眩しげに私を見上げる祖母の声が潤む。私を囲む家族の笑顔の中、私は鏡の中の自分の姿に眼を見張り、喜びと感動の渦の中にいた。
すると突然立ち上がった祖母は、晴着の躾糸をピッピッと切り乍ら、凛とした声で、
「ええか、きっと達者(まめ)で着破るんだよ。ええな。約束だよ。」
と厳しく念を押した後、ひび割れてがさついた手で優しく何度も私の背を撫でた。
「ありがと、ばあさま、私、約束する。きっと達者(まめ)で破れる迄大事に着るから…。」
その時私は今日迄、祖母が私に注いだ愛を連鎖的に蘇らせ、ただ感謝の涙にくれた。
あれから六十年余、この着物をどれだけ着ただろう。結納を始め長女の宮参りなど、あらゆる晴の席には何時も私と共に在(あ)った。唯一そうでなかったのは、六十代半ばで急死した祖母の葬儀だった。周囲の反対を押し切り、私は晴着の上に黒羽織を重ねて祖母を送った。そうしないではいられない私であった。
やがて巷には物が溢れ労せずして入手出来る豊かな時代となったが、私にとって祖母の生命を宿したこの着物への愛着は他と比べようもなく、その後も年令相応に染め直して着用してきた。しかし染め直す度に布地は薄くなり色も褪せてしまったので、十年余り前、大切な着物は私の手で四枚のちゃんちゃんこに姿を変えたのである。
長女と大学生だった孫に由来を語って一枚づつ、あとの二枚は手許に残したが、十年の歳月に一枚は破れてしまい、今は最後の一枚が冬の寒さから私を守ってくれている。
最愛の夫が逝って一年。失意の中で無気力になっていた私に、この冬の凛とした寒気は喝を入れ、ちゃんちゃんこのぬくもりは祖母との固い約束を再認識させた。
明治生まれの気骨ある祖母の「達者(まめ)で着破れ」は、つまり「丈夫で長生きせよ」との私に対する強い願望だった事を痛感する。
傘寿を目前に新たな目標を得た私は、このちゃんちゃんこが擦り切れて破れる迄、達者(まめ)で働き続け祖母との約束を立派に果たそうと思っている。