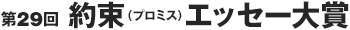2009年
第14回入賞作品
佳作
「満員電車で座る法」 山崎 新一郎(36歳 会社員)
『今度飲みに行きましょう』
社会人なら一度は耳にした事があるだろう。約束と呼べるのかも怪しい、この挨拶にも似た社交辞令のような口約束を。
かくいう私も何度これを口にしたかも分からない。気づけば十年も都心に通うサラリーマンである。
毎朝、同じ時刻の電車に揺られて会社に向かう日々が続いていた。
座って通勤する為に早起きし、始発駅で各駅停車の電車を並んで待つ。
いつもの改札、いつもの車両、よく見る顔ぶれ。
どこかの会社の課長か係長あたりか。毎日同じ、くたびれた背広だ。あのOLもよくこの車両にいる。美人だな。このおばさん、いつも牛乳を飲む。といった感じで、永らく同じ電車に乗っていると、生活リズムが同じなのだろう、他の乗客の面々も大体は決まっている。
並んで始発を待つも椅子取りゲームに敗れて座れなかった日は、乗車距離の短い人を覚えておき、その人の前に立てばよい。その先は座れる。
稀に帰りの電車でもその中の誰かを見掛けて、目が合うとお互いに気まずかったりして、向こうも気付いているのだろう。
そんな毎日が五年以上も続いていたある朝、私の隣に係長(私が付けたあだ名)が座った。彼が座る際に私が少し詰めてスペースを空けた事もあり、係長は少し私に会釈したように思えた。
私と係長は同じ駅から同じ車両に乗り約一時間の通勤時間で、係長は私の降りる駅の二つ手前で降りる。ほぼ毎朝、そのうえ五年も顔を合わせていると妙な親近感も生まれるが、意思の疎通などは果たしていない。
その状況を乗せた電車が発車し十五分ほど経過した時、いつもの日常から外れた。
私と係長が座る正面に吊り革を握って立つ中東風の外国人男性二人が突如、肩から下げていた鞄から大型ラジオのような機械を取り出し、何やらカチャカチャとスイッチを操作し始めた。
刹那に私と係長は見開いた目を合わせ、無言のまま意思疎通を果たした。
決して外国人を差別する訳ではないのだが、その時は『列車爆破テロ』という意味のアイコンタクトが瞬時に成立したのだ。
とっさに二人で次の駅で開いた扉から電車を降りた。
通勤途中の、降りた事もない駅のホームに立つサラリーマン二人。重い口を先に開いたのは係長だった。
「爆弾、ですかね。」
「僕にもそう見えました。」
緊急事態で他人を見捨てて避難し、その結果自分だけ助かっても罪には問われない事を『カルネアデスの板』というらしい。正当防衛の延長である。
しかし、こっそり二人だけ危険から逃亡した罪悪感のような、背徳感のような意識を共有しながら、私と係長は無言で後続の電車に乗った。
この一連から駅員に何かを伝えようにも、何を言えというのか。たぶん思い違いだ。
ラッシュの時間帯なのでもう座る事は出来ない。他人の息づかいも身近にざわめくような満員の車内だ。妙な会話も憚られる。べっとりとした手で吊り革を握りながら、二人は列車が緊急停止しないかと無言のまま脂汗をかく。
そして結局、何事も起きぬまま電車は私が降りる二つ手前の駅に到着し、顔色のすぐれない係長が軽く会釈をして車両を降りる。
「近々飲みにでも行きましょう。」
この社交辞令にも似た一言の約束を私に残して。
見事この口約束は、その週末に果たされる。
安堵の酒を飲みながら焼き鳥を頬張る係長の名刺の肩書は、本当に海運会社に勤める係長であった。いつもより約十分遅れて出社したその日以降、私と係長は何度も列車事故のニュースをチェックしていたがついに何も起きなかった。あの外国人二人も、それ以来見ていない。一体あの機械は何だったのだろう。まさか本当にラジオだったのだろうか。結局その謎は残ったまま日常に戻った。
あれから一年余。今日もまた、草食サラリーマン二人は満員電車から吐き出されていく。
そして満員電車で座る為に一度、試してみたい方法がある。
吊り革に掴まって旧式の大型ラジオを操作するとよいかも知れない。