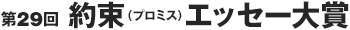2014年
第19回入賞作品
佳作
「妻の言葉、そして約束」 辻川 定男(62歳 無職)
妻は左半身マヒの重度身体障がい者である。足に補装具を付け、右手に杖を持てばなんとか数メートルは歩けるのだが、普段は車いすでの移動となる、もちろんその車いすを押すのは私と決まっている。
数年前、わたし(五十四歳)妻(四十五歳)で、わたしたちが暮らす福井から名古屋にでかけた。名古屋での移動は地下鉄が便利である。もちろんわたしたちも車いすのまま地下鉄に乗った。車いすを「車いす専用スペース」に置き、ロックをかければ車いすはもう動かない。手を離しても大丈夫だ。
車内は混んでいて、わたしの座る場所はなかった。そのとき、わたしは何を思ったのか、妻の杖を手にとって、通路に立った。深い考えはない。ちょっとした悪ふざけのつもりだった。すると近くに座っていた若い女性が「どうぞ、こちらへ」と、わたしに席を譲ってくれた。どうやら杖を持つわたしを障がい者と思ったようである。
わたしは特になにも考えず、その席に座った。なにげなく妻を見やると、険しい顔をしている。障がい者のふりをして、その若い女性をだまし、席にすわったと、思っているようである。そのとき初めてわたしのしたことが悪いことだと気がついた。わたしはなんとも気まずい思いになった。ちょっとした悪ふざけのつもりが今さら、「あ、違うんです」と言うわけにもいかない。わたしは気まずい思いのまま、ずっと下を向いたままで、妻と視線を合わせようとしなかった。
そのまま電車は進み、次の駅に着くと、一人の老婦人が乗ってきた。車内は混んでいたが、誰も席を譲ろうとしない。わたしも躊躇していた。今ここで席を譲ったら、わたしが「ニセ障がい者」だということがまわりの乗客たちにばれてしまう。
そのときだった。妻が車内中に響きわたるほどの大声でわたしに向かって、「定男、その方に席を譲りなさい」と言った。言ったというより、叱りつけたというほどの迫力だった。妻は普段はわたしのことを、「ねえ」とか、「ちょっと」とか呼ぶ。だが、そのときは「定男!」と呼び捨てにした。それほど腹に据えかねたのだろう。でもそれではわたしの名前までばれてしまう。
わたしはびっくりして飛び上がり、その老婦人に席を譲り、妻の車いすの後ろに立った。わたしが「ニセ障がい者」だということがまわりの乗客たちにすっかりとばれてしまった。
車内中の人が、「障がい者のふりをしてまで座りたいのか、サダオ」と囁きあっている(ように、わたしには思えた)。さきほどわたしに席を譲ってくれた若い女性も、「私の厚意を無にした、サダオ」と思っている(ようにわたしには思えた)。車内中の人が軽蔑のまなざしでわたしを見ている(ようにわたしには思えた)。
わたしはなんとも恥ずかしくなって、誰とも視線を合わせないように外の景色を見ていた。地下鉄だから景色など見えるはずもないのだが……。
帰りのJRの車内で、妻はわたしに涙ながらに訴えた。
「もうあんなバカなことは止めて。あなたのしたことは私だけでなく、障がい者みんなを侮辱したのよ。分かっているの?。もうあんなことはしないって、今ここで約束して」
いや、そんなおおげさなことではなく、と反論しようとしたが、妻の涙が拒んでいる。わたしは小さな声で、「はい……」と言うしかなかった。
あのときの妻の言葉が今も耳から離れない。もう七年もたったというのに。