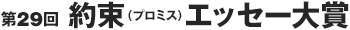2014年
第19回入賞作品
佳作
「オール百点の約束」 堀 宗一朗(56歳 自営業)
その昔、鉛筆は小刀で削るものだった。ところが昭和三十五年十月。当時の浅沼稲次郎社会党委員長が演説中に、十七歳の少年に刺殺された。これを契機に刃物を持たない運動が広がり、子供達からナイフやカミソリと云った危険物が取り上げられ、これが鉛筆削り機の普及に一役買うことになった。云わば鉛筆削り機は、人命尊重の精神を高めることになった世相の産物とも言えるのだ。
などと大局的なことはさておき、私が小学校六年の時、グルグルと手で回す手動の鉛筆削りが、二つ違いの妹と兼用で一台あった。が、実はこれが大の苦手で、鉛筆がどうも上手く削れないのだ。何故なら私は左利きで、ハンドルを手前に引くようにして、グルグルと回さなきゃならないから、やりにくくて仕方ない。カッターも刃が右利き用だから、これも上手く使えない。とにかく世の中は右利き有利に成り立っているから、私のような少数派には非常に不便な仕組みが多かった。ところが時代は進歩する。私は新人類と言われた世代だが、その『新』と付く理由の一つに、自動鉛筆削り機が誕生したと云うことだ。私と妹は早速に両親に懇願した・・・が、
あっさりと拒絶された
そりゃそうでしょう。この頃の自動鉛筆削りは三千五百円前後の値で売られていた。消費者物価指数で現在の価格に直すと、約一万円程度する。そんな高価な機械を使って鉛筆を削る必要がどこにある。これが両親の言い分だ。そこを突かれると返す言葉を失う。それでも私達は諦めなかった。押しの文言は『勉強するため』その一言のみだ。毎日毎日、念仏のように唱えていると、とうとう両親から一つの条件を提示された。それは今度の四教科(算国社理)のテストで、オール百点をとったら買ってやると。
「本当に、絶対だよ、約束だからね!」
勉強にはいささか自信があった。ようし、オール百点、意地でもとってやる。
「お兄ちゃん、頑張って!」
「おう、任せとけ」
その日から猛勉強が始まった。問題は算数。どうも文系型らしく、数字が素直に頭に入ってこない難がある。でも今度だけはそんなことは言ってられない。勉強に勉強を重ねた。今思えば大学受験の時より、この時の方がよく勉強したんじゃないだろうか。それ程、夜を徹して勉強に集中した。その結果、国語、社会、理科は見事に百点をとった。でもやはりと云うか算数だけは、後四点足りていなかった。夢の自動鉛筆削り機を袂まで引き寄せていながら、寸前で掴み損なった。痛恨の極みと云う言葉があるが、私は若干十二歳にしてその意味を骨身に染みて味わった。だがある日、学校から帰ってくると、私と妹の並んだ勉強机にまたがって、夢にまで見た自動鉛筆削り機が光輝いて置かれてあった。これは一体・・・オール百点の約束は果たせなかったけど、その為によく頑張った姿に両親が、四点をおまけしてくれたプレゼントだった。もう嬉しくて嬉しくて、妹と二人で鉛筆を次から次へと削って、その喜びを味わった。そして気が付いたことが二つ。一つは、鉛筆を差し込んでいるとどんどん削るから、新品の鉛筆がたちまち小さくチビた鉛筆になってしまう。音に酔いしれていると、実に不経済な代物になってしまうこと。二つ目は、何故に妹がこの鉛筆削りを使っているのかと云うこと。これはテストを頑張った私へのご褒美であって、君にその使用権利はあるのかい?
「二人で仲良く使いなさい」
これが四点をおまけしてくれた両親の条件だった。釈然とはしないが、兄として度量の大きさを示す他、仕方がなかったわけで・・・
平成の今の世、自動で削れ具合を調整する機能が付いた鉛筆削りがあるが、昔程子供は鉛筆を使わない。実家には今もあの時の自動鉛筆削り機を保管してある。これは私の誇りの逸品だから、決して手離すことはない。