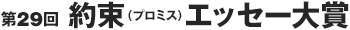2024年
第29回入賞作品
大賞
父の言葉と僕の背中 宮﨑 純大(13歳 中学生)
分厚い教科書と資料集に、学校から貸し出されているノートパソコン。通学用のリュックが重く肩にめりこみそうだ。思わず背中を丸めたくなり、歩く足を止める。
「背すじを伸ばせ」
父の言葉が頭に浮かぶ。僕は大きく息を吐き出してから、前を向く。太陽が力任せに道を照りつけ、セミが何の遠慮もなく大合唱を続ける。ぬるく弱い風が首にまとわりついて余計に汗を呼ぶ。それを軽く手の甲でぬぐい、僕は背を伸ばした。
小学生男子の登校班がすぐ横を通る。黙々と歩く子。ずっと喋っている子。僕も二年前まではランドセルを背負っての登校だった。六年生では班長もした。ついこの間のように思えるし、ものすごく前のことにも思える。
父は僕を毎朝見送っていた。振り返ると父が玄関の前で手を振った。僕も父に手を振った。小学生の頃は、それが普通だった。今は振り返ることはないし、さすがに父も中学生となった僕を見送りはしていないだろう。
信号で待つ。いつもここで引っかかる。タイミングなのだろうか。赤信号をじっと見るのも退屈なので、すぐ横にあるコンビニに目をやるのが習慣のようになっている。駐車場の端にあるのぼりは、もう何年も同じものだと思う。それは軽く揺れていて、大きくこう書かれてある。
「プラモデルあります」
変わったコンビニだと思っていた。小学生のとき、ここで父にプラモデルを買ってもらった。ティラノサウルス。うれしかった。組み立てはすこし難しく、父に手伝ってもらった。今でも自分の部屋に飾ってはいるが、すっかりホコリをまとっている。
信号が青になる。背筋を気にして歩く。中学校の目の前は公民館で、ここで四年生の夏休み、「親子陶芸教室」が開催された。父はそれに申し込み、二人で参加をした。その機会をとおして陶芸に興味をもってほしい、という願いがあったのだと思うが、そこで作ったお皿も、ティラノサウルスと同じくホコリを乗せている。
陶芸に限らず、父は多くのきっかけを与えてくれた。サッカー、水泳、ギター、絵画、メダカの飼育などなど。しかしそのどれも熱中するというまではいかず、なんとなくやめてしまっていた。
学校に到着。汗がふき出て止まらないでいた。ポケットからハンカチを出すのも意味がないと思えるくらいの汗だった。運動場が目に入って、思い出したのは小学校のマラソン大会のことだった。その日の仕事はどうしたのだろうか、父は見に来てくれた。
最後の直線、父の声が聞こえた。
「前のやつ、抜かせ!」
僕は力を振り絞った。その全力の背中を父は確かに見たと思う。
「あの言い方は前の子に悪かったな」
帰宅してから、「今日はよく頑張ったな」のあと、父はすまなそうにそう言った。
教室に入り、ダンベルが入ったようなリュックをおろす。先日の参観日も、父は来てくれた。道徳の授業で、父は廊下から見ていた。僕は父を一度だけ見て、それからは見なかった。小学生の頃は良い格好を見せたくて張りきって手をあげ、発表に励んでいた。
いまでも覚えている。学童保育所に迎えに来たときの父の顔。バス旅行でお弁当を作ってくれて、美味しかったと伝えたときの父の顔。公園でサッカーのドリブルをしたときに、おまえ結構上手いなと言ったときの父の顔。
良い成績を取れと言われたことは一度もない。いつも言われるのは、
「背すじを伸ばせ」
これが僕と父との約束。
振り向き手を振るかわりに、まっすぐ前を向いて歩いていく。その背中を父に見せる。人生という道の、暑い日も寒い日も。
チャイムが鳴り、僕は背すじを伸ばした。