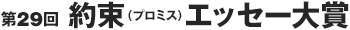2024年
第29回入賞作品
優秀賞
一方的な約束 高垣 香月(29歳 主婦)
「爪、切ってほしいねん」
そう頼まれたわたしは差し出された手の長く伸びた爪をチラリと見て、「わかりました。また後で切りに来ますね」と答え、ささっと次の患者の体温を測りに向かった。
今、立ち止まっている暇はない。これから二十数人もの体温や血圧を測り、四十人ものおむつ交換をして、異常があれば報告と対応をして記録を書き、点滴や塗り薬も行わなければならない。そうこうしているうちに、ガチャンと大きな音と共に昼食の台車が到着する。その前に寝ている患者を一人ずつ起こして食堂に案内しないと。走りまわっている間に、患者が廊下で放尿する。呼び止められれば何度も同じことを言われ、いけないと思いながらも笑顔がだんだん萎れてくる。でもこれがわたしの仕事。認知症専門病棟で毎日のように走りまわる。
業務に追われながら、さっきの患者のシワが深く刻まれた手と長く伸びた爪がちらっと頭をよぎる。なんとしても業務を早めに終わらせて、あの患者の爪を切る時間を確保したい。だってそう約束したから。
認知症の患者は言うことがコロコロ変わる。そんなことを言った覚えはない、と怒られることも日常茶飯事だ。けれど、わたしは爪を切ると約束したことを覚えている。たとえその約束をすぐに忘れてしまう相手でも、わたしが覚えている限りは約束を果たさなければならない。忙しいことを理由にその約束をなかったことにしてしまったら、わたしの胸の中に小さな棘が刺さって、チクチクとわたしを責めてくる。小さな棘でも気になって仕方がない。
患者のおむつを交換し、体調を確認し、食事の介助をする。その合間にも気になることが増えていく。この人も爪が伸びている。この人は服がひどく汚れている。この人は髪の毛が絡まっている。そうして心の中で、必ず戻って来るからね、とどんどん自分勝手に約束事を取り付けていく。
ようやく最後の看護記録に手をつける。パソコンのキーボードを叩きながら、時計を見る。十分くらいは時間が取れそうだ。記録を終えると、手袋をして、爪切りを手に取った。
爪を切ってほしいと頼んできた患者は、食堂の椅子に座りテレビを見つめていた。「こんにちは。爪が伸びてきていますね。よかったら切りましょうか」と声を掛けると、ぱっとこちらを見て、「悪いなぁ。ここんとこがなぁ、ひっかかってしもて」と自分の手をさすっている。わたしは隣の椅子に座り、その冷えた手を包み込んだ。年がいくにつれて硬くなってしまった爪をパチン、パチン、と痛くないように気をつけながら丁寧に切る。さっきまで無気力にテレビを見つめていた患者の目は、光を帯びながら自分の短くなっていく爪に釘付けになっている。「あんた、上手に切るねぇ。嬉しいわぁ。ありがとう」と、その十分足らずのわたしとの交流を悦ばしく思ってくれているようだった。
わたしは看護師の仕事の中では些細なことと思われている小さな約束を守ることを大切にしている。ある男性が息を引き取った時だ。冷たくなったその口元には、細かい髭が生えていた。朝、後で剃りに来る、と約束をしたのに。彼が生きている間にさっぱりとした感覚を味わってほしかった。わたしは彼との約束を守れなかったのだ。冷たい頬に手を当てながら最後の髭剃りをした。生きていたら、彼はわたしになんと話しただろう。
小さな約束を守ることは、普段ゆっくりと聞くことができない彼らの話に耳を傾け、わたしと彼らの心を温める貴重な時間を生み出すわたしの大切な営みなのだ。たとえそれが、彼らの一瞬の記憶の中だとしても。