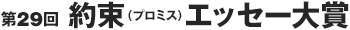2024年
第29回入賞作品
佳作
ぶどうと青りんご 田中 千遥(17歳 高校生)
盗っちゃった…。もう何年前なのかも思い出せないくらいなのに、まだ手のひらの中にある2つの飴の感触が忘れられない。
時をさかのぼること十数年前の月曜日、私は通っていた英会話教室の中にいた。レッスン中にいつも考えていたのは「今日は何味の飴貰おうかな…。前はイチゴ味だったし、今日は…。」という、まあくだらないことであった。だが、当時の(いや、今も)私の食に対する執念はすさまじかった。どれくらいかと言うならば、せんべいを半分こして食べる時も、「半分」にしたくて粉々になるまで割ってから分けるほどだった。そんな私は英会話の後に先生から貰える一粒の飴が大好きだった。日本のスーパーで買える物もあれば、海外の物まで、色々なものがバスケットに入っていて、当時の私には、それはそれは美味しそうで、まるで光り輝く宝箱のように見えていた。
だが、事件は突然やってきた。どうしてもぶどう味も青りんご味もほしかった。どうしても。「ちはるちゃーん、お迎え来たよー。」先生がそう言った瞬間、私はとっさに両手に持っていた2つの飴をポケットに隠してしまった。そのまま母の運転する車に乗り、家まで帰るたった15分の時間、あんなに寒いのに私は冷や汗ばかりかいていたのを覚えている。やってしまった…。返すタイミングすら失ってしまった。バスケットの前でうなりながら迷うほど欲しかったはずなのに、何だかちっとも嬉しくないし、何なら胸がモヤッとする。(後に私はこの感情がいわゆる「罪悪感」ということを知る。)そんな事を考えている間に家に着いていた。ボーッとしながら靴を脱ぐ時、気を抜いていた。緑と紫の小さい袋が2つ、ぽろりとポケットから出てきた。その日2回目のやってしまった…である。
「ちーちゃん、何で2個あるの?」うわ、やっぱりバレた。これはもう、全部言ってしまおう。これまでの事(といっても30分前のことだが)を全て母に話した。すると母は「返しに行くよ。」とまた鍵を取って私を車に乗せた。車の中の記憶なんてない。ただただ心臓の音がうるさいだけだった。
教室の前に着いた。どうしよう、でも、何かモヤッとする。ゆっくり息を吐いて、吸って、また吐くと同時にドアを押す。「先生、あのね…。」
全て、言った。いや、口から出したという表現が合っているのかもしれない。ちらりと先生の顔を見上げた。目が合った瞬間、先生は「正直に言ってくれたんだね、ありがとうね。」と言って笑った。そして「千遥ちゃんはいつも頑張ってるから、大丈夫。ただ、一つだけ約束してね。この教室にいる間は正直でいること。ね?それだけ。」それを聞いて、私はここに通っていて良かったと心の底から感じた。自分の故郷を離れて日本で英語を教える先生が、とてもたくましく見えた。
それから、私は英会話に行くときは「正直に。」と心の中で唱えてからドアを押すようになっていた。そう言うと、なんだか毎回すっきりするのだ。あのときの小さな小さな罪を一瞬だけ思い出して、また償えたような気になる。大げさかと思うかもしれないが、幼い私からすると世紀の大罪だったのだ。そんな事を思い出しながら、私は今日もあのドアの前に立って深呼吸をする。あの日の私を励ますように、ゆっくり、ゆっくり。そして、ぐっと重いドアを押す。「さぁ、今日は何味の飴にしようかな。」