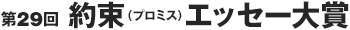2024年
第29回入賞作品
佳作
祖母と干し柿 山浦 彩夏(16歳 高校生)
私は祖父、祖母、父、母、弟と六人で暮らしている。祖父母と一緒に暮らし始めたのは私が中学一年生の時からだ。当初から、老人ホームなど将来入居する施設をそろそろ選んでおきたいという話をしていた。しかし、二人とも元気に過ごしているため施設に入るということは想像できなかった。今でもあまり想像できていない。昨年祖母の兄が亡くなった。それ以降、親戚のお葬式が続いている。そのような中、祖父と祖母は自分たちが亡くなった時のことを相談するようになった。たしかに年齢を考慮すると、今のうちに考えておくべきだろう。しかし、つい最近まで入居する施設の話をしていたのにも関わらず死後の話をするとは、早すぎるのではないだろうか。私はこれまで身近な人が亡くなった経験があまりないため、毎日会っている人が突然いなくなる感覚がわからないが、きっと寂しく受け入れがたいことだろう。私や弟が一度でも好きだと言ったものや、美味しいと言ったものは私たちが飽きるまで買ってきて「これ好きでしょ。」と言って嬉しそうに渡してくれる祖母。普段は冗談ばかり言っているが、悩んでいる時や落ち込んでいる時には相談に乗って元気をくれる祖父。二人がこの家からいなくなった日々を想像するだけで怖くなる。
毎年冬になると祖母は渋柿を買ってきて、自分の部屋やベランダに干して干し柿を作る。私は早く甘くなれと渋柿を急かすかのように毎日祖父母の部屋に通い、あと何日で食べられるかと祖母に尋ねた。やっと食べ頃になり、祖母がビニール紐から外して渡してくれた干し柿を口いっぱいに頬張っていると「彩夏ちゃんは美味しそうに食べてくれるから、作ってよかったって思うよ。ばあちゃんが死んだら、ここで干し柿を作ってたなって思い出してほしいな。」と祖母が言った。どうして突然そのようなことを言うのだろうか。軽く死後の話をしているが、怖くないのだろうか。干し柿を食べたいという一心だった私には、重すぎる話だった。どのように返事をするべきかがわからず黙っていると、祖母が続けて言った。「昔は死ぬのが怖いと思っていたけど、最近は怖いと思わないんだ。今はばあちゃんのお兄ちゃんもお姉ちゃんもみんなあっち側にいて、私のことも迎えに来てくれたんだな、みんなに会えるんだなって思う。」祖母は真面目な顔をした後、干し柿のようにしわを作って笑った。祖母なりに死に対して向き合っているのだろう。私も今の祖母と同じ年齢になった時、同じように考えるのだろうか。干し柿を片手に横目で祖母を見て話を聞いていた自分が、なんだか恥ずかしく思えた。近くにいた祖父も祖母の話を黙って聞いていた。
最近、祖母の忘れ物が増えてきたように感じる。もともと忘れっぽいところはあったが、より目立ってきている。将来認知症になってしまったらどうしよう。私たち家族を見ても誰なのかわからなくなってしまうかもしれない。考えると不安になるが、たとえ祖母が私のことを忘れてしまっても、私は干し柿を見た時、忘れることなく祖母を思い出したい。喧嘩をしてしまう日もあれば、仲良しの日もある。今何気なく過ごしている一日一日をずっと覚えていたい。私の弟はあまり干し柿が好きではない。弟だけでなく、父も母もだ。私にしかできない祖母との約束。あと何回この味を食べられるのだろうか。また来年も食べてほしい、まだまだ生きていたいと祖母に思ってもらうためにとっておきの笑顔でありがとう、美味しいと言い続けたい。