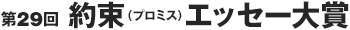2024年
第29回入賞作品
佳作
ある生徒との約束 後藤 里奈(36歳 教員)
心が折れそうになると、いつも読み返す手紙がある。小さなメモ用紙に書かれたそれは誤字だらけだが、なんとか思いを届けたいという真摯な気持ちがひしひしと伝わってくる。これを読む度、「私もまだまだ頑張らなければ」と身が引き締まる。
今から十四年前、私は念願叶って教師となった。教員を志したのは、中学生の頃に読んだ小説「二十四の瞳」がきっかけだった。子供たちに慕われ、どんな逆境にもめげない若き女性教師・大石先生に憧れたのだ。素直な子供たちに囲まれ、熱く人生訓を語る私―。いつしかそんなイメージが自分の中で膨らんでいった。だが、憧れの教壇に立てたのも束の間、私の「理想の教師像」はあっという間に打ち砕かれてしまう。私が初めて赴任した学校は、いじめや非行、不登校などで、一般の高校には通えなくなった生徒たちが多くいる「サポート校」だったのだ。
期待と不安の入り交じるなか迎えた新学期、私を待っていたのはきらきら光る瞳ではなく、こちらを試すかのように睨みつけ、すべてを拒絶するかのような死んだ目であった。初めて接する不良の生徒たちに戸惑いながらも、最初のうちは「だからこそやりがいがあるのだ」と意気込んでいた。
だが現実は厳しく、私の認識は甘かった。授業中の私語や飲食、携帯ゲームは日常茶飯事。ひどいクラスでは人目をはばからず化粧をしたり、喧嘩が始まることもしばしば。恐る恐る注意をすれば、無視されるか「うざい」「新人のくせに」と憎まれ口を叩かれる。少しでも学習に興味を持ってもらおうと自作のプリントを配れば、私の努力はたちまち紙ヒコーキとなって教室中を飛び交い、授業後にはくしゃくしゃに丸められて床に捨てられていた。保護者に事情を話せば「そっちの指導が悪い。教師失格なのでは?」と責められる。同期の仲間たちも「割に合わない」「やってられない」と言って一人、また一人と辞めていった。教師になることは、亡き親友と共に目指してきた夢でもあったが、教職への理想と情熱はもはや消えかけていた。
そして半年後、我慢の限界に達した私はついに辞職を決意した。私はこんな思いをするために教師になったわけではない。もっと普通の学校で働こう―。その日、授業を終え、いつものように逃げるようにして教室を出ていくと、「先生!」と、ある女子生徒が私の後を追ってきた。自分のことを「先生」と呼んでくれるのは彼女だけだったので、印象に残っている生徒だった。その子が突然「これ、読んで下さい」と言って私にメモ用紙を手渡し、立ち去っていった。驚くことに、それは私への手紙だった。そこには「いつもクラスが騒がしく、先生に迷惑をかけてすみません。でも私は、そんな中でも一生懸命な先生の姿に勇気をもらっています。だからこれからも、先生を辞めないで下さい。」と書かれていた。
彼女は、今日私が辞表を出そうとしていたことを知っていたのだろうか。半ば投げやりになっていた自分の姿が、そんなふうに映っていたなんて―。私はその場で何度も手紙を読み返し、持っていた辞表を破り捨てた。今まで「報われない」と思っていたのは、事実報われる資格のない自分であることにほかならなかったのだ。不格好でも衝突してもいい。もう一度、目の前の生徒と本気で向き合ってみよう。そう決意した。
あれから十四年。私はなんとか彼女との約束を守っている。年を重ねるごとに、教師に「なる」ことよりも「なり続ける」ことの方が難しいと痛感している。どれほど固く交わされた誓いも、それだけでは意味がない。約束を守るには、それを実現させるに足るだけの努力が必要なのだろう。あの時受け取った手紙は、初心を思い出させてくれる大切なお守りだ。彼女との約束を胸に、私は残りの教員人生を全力でまっとうするのみだ。