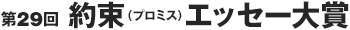2024年
第29回入賞作品
佳作
渡辺 吏乙渚(14歳 中学生)
毎年十二月に入った頃くらいから、我が家では誰からともなく
「今年の年越、どうするん。」
と議論が始まる。それは、何を食べる?とか、どこに行く?とかといった一般的な行事のことではない。「家族四人で年を越えるその瞬間、全員でどんなパフォーマンスをしながら新年を迎えるのか。」を話しあうのだ。ある年は四人全員で円陣を組んでぐるぐる回り、歓声をあげながら新年を迎え、またある年はみんながソファーから手を繋いで飛んで、四人が空中にいる間に年を越したこともある。かれこれ私が物心ついたときからやっているから、十年以上やっていることになる。もはや我が家の数あるイベントの中でもトップクラスに重要なルーティンになっているのだ。
私には八歳上の兄がいる。「りっくん」は私が生まれると知った時とても喜んでくれたらしい。いつもひとりで遊んでいた自分に、生涯の友だちができたような感じだったんだ、と聞いた。一番喜んでた、とその時の話を両親は今でも笑い話のようによく口にする。私にとってもりっくんは一番の友だちだ。学校から帰って真っ先に話すのはりっくんだし、ゲームをするのも、カラオケをするのも、ピアノを演奏するのも全部りっくんと一緒にする。また兄としてのりっくんも最強だ。とんでもなく頭が良くて難解な問題もスラスラ解いてしまうりっくんは大学受験の多忙なときにも、小学生の私に嫌な顔ひとつせず、親のように優しく勉強を教えてくれた。そんな大好きなりっくんが今から四年前、大学進学によって我が家から巣立ってしまうかもしれない、という私の人生最大のピンチが訪れた。落ち込む私に無関心のように、その年の瀬がお構いなしにやってきた。
その年のパフォーマンスは、「四人全員がひとかたまりになっておんぶに抱っこしながらの年越!」だった。家族みんなが来年から四人で年越できなくなる可能性を感じながら誰一人そのことに触れなかった。両親もりっくんも私と同じように寂しいんだ、と思った。
「今年も残りあと一分となりました。」
と、テレビからアナウンサーの無機質な声が聞こえたとき、りっくんが小さな声でぽつぽつと話し始めた。これまでの感謝の気持ちを両親に伝えたあと、私に向かって
「来年も、再来年もずっと家族四人で年を越そう。」
と約束してくれた。なんとも言えない感情が込みあげてきてやがて胸がいっぱいになった。そのまま新年のカウントダウンが始まり、急いでパフォーマンスの準備に取り掛かった。気づいたら涙で顔がぐちゃぐちゃになったまま、りっくんの背中に力いっぱい抱きついていた。りっくんの背中はビチャビチャに濡れてしまった。私の幸せは、りっくんと両親の存在によって作り出され、満たされていたんだ、と気づいた。幼かった自分でもそのことに気づくことが出来たのは、毎年このルーティンがあったおかげなのかもしれない。
その翌年、りっくんは地元の大学に無事進学した。「ひょっとして今年も四人で年越できるんじゃない?」とほくそ笑んだ私。まだ四人で暮らせる。
今年もあと数日となった。今年も家族四人だ。すでに開かれた十二月の家族会議で、
「みんなでピラミッドを作って年越!」
と決まった。どうやってピラミッドを作るのかはさておき、当然のことながら私が一番上なのは決まっている。高いところから私の大好きな三人を独占しよう。
りっくんは地元の企業に就職が決まり、来年四月から晴れて社会人となる。地元の会社だけど赴任先はどこになるか分からないらしい。今度こそ本当に遠くに行ってしまうかもしれない。でももう寂しくない。四年前の約束はきちんと守ってもらうから。